前回の続き。
どこでもないどこかへ
平日の昼間、人気のない記念公園の公衆便所の個室に、ぼんごはいた。
なんでこんなことになっているのだろう。
なんで自分はこうなんだろう。
なんで世の中は自分を突き放して回るのだろう。
昔は、病室や看護師さん、お医者さんが自分を守ってくれていた。
父や母も自分の身体を世界で一番大事にしてくれていた。
いつからだろう。
自分を守ってくれるはずの存在はしだいに自分から遠ざかっていて、いつの間にか無くなっていた。
このころは自分がパニック障害であることがわかっていなかったから、体調不良の原因を病気のせいにもできず、有効な対策もとれず、体当たりで世界に向き合うことしかできなかったのだ。
今やもう、自分を自分として受け入れてくれるのはこの薄汚くて黴臭い公衆便所の一室の空間くらいしかない。逃げる場所はここしかないように思われた。
目の奥からじわじわと自分の感情を乗せた液体があふれて、しばらくの間それは止まなかった。
この頃、ぼんごはぼんごで度重なる体調不良や周囲との付き合い方にすこしだけ慣れもでてきていて、それは、本人曰く置物のようにじっと静かにしていればいい、というもので、外界の圧に対して感情をシャットダウンするような、無の境地のような、要は気にしなければいい、言わしておけばいい、といった感じの態度をとるやり方で、その考え方は発作が起こらなければそれなりに働いて、ちょっと達観できる時もあったようなのだ。
そういった態度は、いつまで続くのか、いつになったら終わるのかわからない発作を幾度となく乗り越えるうちに本人の試行錯誤によって到達したもので、自分と世界との折り合いをようやっと掴み始めた、ぼんごなりの自分自身の壁の再生を試みる努力の結果だったはずなのだ。
それでもなお発作は起こるし、そういう時は仕方なし、一時的に壁を借りるような感じで、消極的な選択で保健室に来ているのであって、好んで保健室に来ているわけじゃないのだ。
だから、保健室のおばちゃんの「あなたはここにいてもできることもなし、ただ椅子に座っているだけだから教室にいて座っていてもそのうち治るでしょ」といった態度はぼんごにとっては投げやりで冷たいものに思えて、その瞬間、保健室も自分を守る場所ではなくなってしまったようなのだ。
それで衝動的に居場所を探したようだった。
探すというか、どこでもないどこかに、自分の手足で逃げ出した瞬間だった。
ぼんごにとって嫌なな出来事だったが、不思議とこの時は地面は固く、筋力はじゅうぶん、酸素もあって平衡感覚もあった。
そこにはパニック発作はなく、自分の意志をはっきり感じて、意図的に逃げた。
I’m with you
1時間くらいして、ぼんごは自分が上履きのまま出てきたことに気づくくらいには、感情が戻った。
で、急に恥ずかしくなってきて、学校に戻って荷物を取って靴を履き替えないとな、と冷静に思った。
教室に帰ると、クラスメイトが話しかけてきて、S子がぼんごを探しに行ったよ、と教えてくれた。
S子はよくぼんごを気にかけてくれる子で、3年間クラスが一緒で、ぼんごが学校に行けなかったときは授業の進みを教えてくれたり、体調不良を心配してくれたりと、いろいろと気にかけてくれる子で、勉強もスポーツもできる優等生だった。
ぼんごが学校を出たあと、そのまま何事もなく、授業は始まったそうな。
しばらくすると、いつもの保健室の先生が教室にやってきて、教室の様子をちらと確認すると、S子を呼んで、ぼんごが保健室にいない、ここにもいないし行方知れずになっている、といったようなことを伝えたらしい。
いつもの保健室の先生はS子の部活の顧問でもあって、二人とも、ぼんごと話をする人たちだった。
S子は保健室の先生の言葉を聞いて、授業中にもかかわらず先生に断ってぼんごを探しに出た。
ぼんごは上履きのまま学校を出たから、S子は下足箱に靴があるのを確認して、ぼんごは学校の中にいると考えて校内を探し回った。きっと1時間か2時間か、探してくれていたのだと思う。
ぼんごが戻ってしばらくすると、S子が教室に戻った。
「ああぼんご、よかった」とそんな安堵感に満ちた言葉を言われた。
それで話をして、S子が自分を探し回ってくれていたのを知った。
ぼんごは悪い事をしたと感じた。ごめんね、と伝えた。
ぼんごが気づいていないだけで、いつもぼんごを見守ってくれる人たちも、そこにはいたのだ。
そこにはぼんごに対する優しさだけがあって、他人の意志をはっきり感じて、ぼんごは自分の行動を反省した。

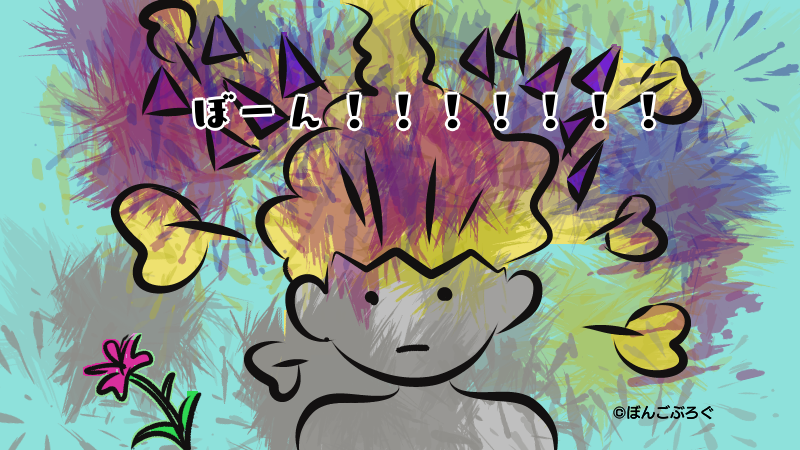
コメント